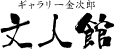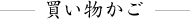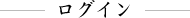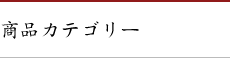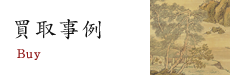静かだった。
由布岳の原生林へと続く森から聞こえてくる木々のさざめきや
鳥のさえずりとともに心地よい風が吹き込んでいた。
大きな壁面いっぱいにズラリと掛けられた古い木彫の仮面たちが、
森の声に呼応しささやいているかのようである。
想像もできないほどの現実の厳しさに打ち拉がれる状況が
待ち受けているとも知らず、異空間を漂うように本当に静かな時を過ごしていた。
大学で学芸員資格を取得し、伯父の高見乾司が運営する
『由布院空想の森美術館』に就職した私の仕事はそれほど忙しいものではなく、
時折、前述のような静かな時を過ごすこともあった。
美術館が経営難に陥っていることを知ったのは一年ほどが経ったころのことで、
それからは美術館を存続させるべくまさに東奔西走であったが、
万策尽きてついに閉館せざるを得なくなった。
時が経ち、ある種の大人になった私は、
『あの時、美術館を閉館する必要は無かった』
と思うようになった。
少なからず経済的に立ち行かなくなってはいたが、
それは一時期的なものであったと言うことはさほど強引なことでもないように思うし、
ただその時に示された経済的に即効力のあるプランの方を
銀行が選択し推し進めただけのような気がしている。
「ただ世に評価された名画を展示するだけの箱物美術館ではなく、
美術とは何かを問い、真っ向から美術に向き合い、
それを美術館として実践する、本来の美術館のあるべき姿である。」
といった一定の評価を受けていたにも関わらず、
膨大な収蔵品や資料類を大型トラックに積み込み『空想の森』は去った。
悔しかった。悲しかった。
それでも私は敢えて何かに抗い、立ち向かうために湯布院に残った。
そして、私は書画商としての道を歩み始めたのである。
そして、そして、
ほど近い将来、湯布院に、静かな『空想の森』の
『仮面たち』のささやきが聞こえる日がやってくる。